初診料とは、患者さんが医療機関で初めて診察を受ける際に算定できる診療報酬です。
A000 初診料 291点
初診料の算定要件と加算
注1 保険医療機関において初診を行った場合に算定します。情報通信機器を用いた初診を行った場合については、253点を算定します。
注2 病院である保険医療機関、地域医療支援病院及び外来機能報告対象病院等であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して初診を行った場合には、注1本文の規定にかかわらず、216点(注1のただし書に規定する場合にあっては、188点)を算定する。
注3 病院である保険医療機関の数が400床以上である病院であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して初診を行った場合には、注1本文の規定にかかわらず、216点(注1のただし書に規定する場合にあっては、188点)を算定する。
注4 医療用医薬品の取引価格の妥結率に収載されている医療用医薬品の薬価総額に占める卸売販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第34条第5項に規定する卸売販売業者をいう。)と当該保険医療機関との間での取引価格が定められた薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額の割合をいう。以下同じ。)に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200床以上である病院に限る。)において初診を行った場合には、注1本文の規定にかかわらず、特定妥結率初診料として、216点(注1のただし書に規定する場合にあっては、188点)を算定する。
注5 1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初診を行った場合は、それらの傷病に係る初診料は、併せて1回とし、第1回の初診のときに算定する。ただし、同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、新たに別の診療科を初診として受診した場合は、2つ目の診療科に限り146点(注1のただし書に規定する場合にあっては、127点)を、この場合において注2から注4までに規定する場合は、108点(注1のただし書に規定する場合にあっては、94点)を算定できる。ただし書の場合においては、注6から注16までに規定する加算は算定しない。
- Q同じ日に、1つ目の診療科を再診で受診し、その後に2つ目の診療科を初診で受診した場合は算定可能でしょうか?また、同じ日に1つ目の診療科を初診で受診し、その後に2つ目の診療科を再診で受診した場合は算定可能でしょうか?
- A
いずれも算定可能です。初診の診療科と再診の診療科の順番は特に問われません。
- Q同じ日に3つの診療科を受診する場合は算定できないのでしょうか?
- A
3つ目は算定できないとされています。
注6 6歳未満の乳幼児に対して初診を行った場合は、乳幼児加算として、75点を所定点数に加算する。ただし、注7又は注8に規定する加算を算定する場合は算定しない。
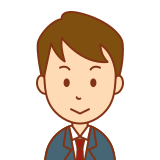
※年末年始(12月29日~1月3日)は休日加算の対象となるため、休診している医療機関で急病などのやむを得ない理由で受診した場合は休日加算が算定できます。
注7 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(平日の深夜(午後10時から午前6時まで)に初診を行った場合は時間外加算として85点(6歳未満は200点)、休日(深夜を除く)に初診と行った場合は休日加算として250点(6歳未満は365点)、深夜に初診を行った場合は深夜加算として480点(6歳未満は695点)を所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険医療機関にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間において初診を行った場合は、230点(6歳未満は345点)を所定点数に加算する。
注8 小児科を標榜する保険医療機関にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜において6歳未満の乳幼児に対して初診を行った場合は、注7の規定にかかわらず、それぞれ200点、365点又は695点を所定点数に加算する。
注9 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る)が、午後6時(土曜日にあっては正午)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く)、休日又は深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間において初診を行った場合は、夜間・早朝等加算として、50点を所定点数に加算する。ただし、注7のただし書又は注8に規定する加算を算定する場合にあっては、この限りでない。
注10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。)において初診を行った場合は、機能強化加算として、80点を所定点数に加算する。
注11 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において初診を行った場合は、外来感染対策向上加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。ただし、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で初診を行った場合は、発熱患者等対応加算として、月1回に限り20点を更に所定点数に加算する。
注12 注11本文に該当する場合であって、感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において初診を行った場合は、連携強化加算として、月1回に限り3点を更に所定点数に加算する。
注13 注11本文に該当する場合であって、感染防止対策に資する情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において初診を行った場合は、サーベイランス強化加算として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。
注14 注11本文に該当する場合であって、抗菌薬の使用状況につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において初診を行った場合は、抗菌薬適正使用体制加算として、月に1回に限り5点を更に所定点数に加算する。
注15 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で初診を行った場合は、医療情報取得加算1として、月1回に限り3点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情報取得加算2として、月1回に限り1点を所定点数に加算する。
注16 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り8点を所定点数に加算する。
初診料の留意事項
(1) 特に初診料が算定できない旨の規定がある場合を除き、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった場合に、初診料を算定する。なお、同一の保険医が別の医療機関において、同一の患者について診療を行った場合は、最初に診療を行った医療機関において初診料を算定する。
(2) 「注1」のただし書に規定する情報通信機器を用いた診療については、以下のアからキまでの取扱いとする。
ア 厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(オンライン指針)に沿って情報通信機器を用いた診療を行った場合に算定する。なお、この場合において、診療内容、診療日及び診療時間等の要点を診療録に記載すること。
イ 情報通信機器を用いた診療は、原則として、保険医療機関に所属する保険医が保険医療機関内で実施すること。なお、保険医療機関外で情報通信機器を用いた診療を実施する場合であっても、オンライン指針に沿った適切な診療が行われるものであり、情報通信機器を用いた診療を実施した場所については、事後的に確認可能な場所であること。
ウ 情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関について、患者の急変時等の緊急時には、原則として、当該保険医療機関が必要な対応を行うこと。ただし、夜間や休日など、当該保険医療機関がやむを得ず対応できない場合については、患者が速やかに受診できる医療機関において対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患者に説明した上で、以下の内容について、診療録に記載しておくこと。
(イ)当該患者に「かかりつけの医師」がいる場合には、当該医師が所属する医療機関名
(ロ)当該患者に「かかりつけの医師」がいない場合には、対面診療により診療できない理由、適切な医療機関としての紹介先の医療機関名、紹介方法及び患者の同意
エ オンライン指針において、「対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められる」とされていることから、保険医療機関においては、対面診療を提供できる体制を有すること。また、「オンライン診療を行った医師自身では対応困難な疾患・病態の患者や緊急性がある場合については、オンライン診療を行った医師がより適切な医療機関に自ら連絡して紹介することが求められる」とされていることから、患者の状況によって対応することが困難な場合には、ほかの医療機関と連携して対応できる体制を有すること。
オ 情報通信機器を用いた診療を行う際には、オンライン指針に沿って診療を行い、オンライン指針において示されている一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」等を踏まえ、当該診療がオンライン指針に沿った適切な診療であることを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、処方を行う際には、オンライン指針に沿って処方を行い、一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを踏まえ、当該処方がオンライン指針に沿った適切な処方であることを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
カ 情報通信機器を用いた診療を行う際は、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。
キ 情報通信機器を用いた診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。
(3) 患者が異和を訴え診療を求めた場合において、診断の結果、疾病と認むべき徴候のない場合にあっても初診料を算定できる。
(4) 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者について、当該保険医が、特に治療の必要性を認め治療を開始した場合には、初診料は算定できない。ただし、当該治療(初診を除く。)については、医療保険給付対象として診療報酬を算定できること。
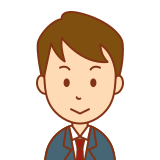
レセプト請求を行う際は、「自他覚症状がなく健康診断を目的に受診し疾患が発覚して診療を行った」という内容を記載して請求を行うことで返戻を防ぐことができます。
(5) (4)にかかわらず、健康診断で疾患が発見された患者が、疾患を発見した保険医以外の保険医(当該疾患を発見した保険医の属する保険医療機関の保険医を除く。)において治療を開始した場合には、初診料を算定できる。
(6) 労災保険、健康診断、自費等により傷病の治療を入院外で受けている期間中又は医療法に規定する病床に入院している期間中にあっては、当該保険医療機関において医療保険給付対象となる診療を受けた場合においても、初診料は算定できない。
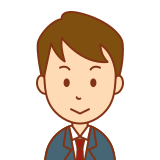
レセプト請求を行う際は、「労災保険にて診療料は請求済み」などの記載を行うことで返戻を防ぐことができます。
(7) 「注2」又は「注3」に規定する保険医療機関において、病院と診療所の機能分担の推進を図る観点から、他の保険医療機関等からの文書による紹介がなく、初診を行った場合は、「注1」の規定にかかわらず「注2」又は「注3」の所定点数を算定する(緊急その他やむを得ない事情がある場合を除く。)。この場合において、患者に対し十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意があった場合には、「注1」との差額に相当する療養部分について選定療養として、その費用を患者から徴収することができる。なお、保健所及び市町村等の医師が、健康診断等の結果に基づき治療の必要性を認め、当該患者に対し必要な診療が可能な保険医療機関を特定し、当該保険医療機関あてに文書による紹介を行った患者については、紹介のある患者とみなすことができる。また、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合(以下「紹介割合」という。)等が低い保険医療機関とは、「注2」にあっては、紹介割合の実績が50%未満又は逆紹介割合の実績が30‰未満の特定機能病院、地域医療支援病院及び紹介受診重点医療機関をいい、「注3」にあっては、紹介割合の実績が 40%未満又は逆紹介割合の実績が 20‰未満の許可病床の数が 400床以上の病院をいう。紹介割合及び逆紹介割合の実績の算定期間は、報告年度の前年度1年間とし、当該期間の紹介割合及び逆紹介割合の実績が基準を上回る場合には、紹介割合等が低い保険医療機関とはみなされない。
※ 紹介割合及び逆紹介割合の計算については、下記のとおりとする。
紹介割合(%) = (紹介患者数+救急患者数)÷ 初診の患者数 ✕ 100
逆紹介割合(‰) = 逆紹介患者数 ÷ (初診の患者数+再診の患者数) ✕ 1,000
なお、 初診の患者数、再診の患者数、紹介患者数、逆紹介患者数、救急患者数については、それぞれ次に掲げる数をいう。
ア 初診の患者数については、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった患者の数とする。
イ 再診の患者数については、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった患者以外の患者の数とする。
ウ 紹介患者数については、他の保険医療機関から診療情報提供書の提供を受け、紹介先保険医療機関において医学的に初診といわれる診療行為があった患者の数とする。
エ 逆紹介患者数については、診療に基づき他の保険医療機関での診療の必要性等を認め、患者に説明し、その同意を得て当該他の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて紹介を行った患者(開設者と直接関係のある他の機関に紹介した患者を除き遠隔連携診療料又は連携強化診療情報提供料を算定している患者を含む。)の数とする。
オ 救急患者数については、地方公共団体又は医療機関に所属する救急自動車により搬送された初診の患者の数とする。
(8) 特定機能病院、地域医療支援病院、紹介受診重点医療機関及び許可病床の数が400床以上の病院は、紹介割合及び逆紹介割合を別紙様式28により、毎年10月に地方厚生(支)局長へ報告すること。また、報告を行った保険医療機関であって、報告年度の連続する6か月間で実績の基準を満たした保険医療機関については、翌年の4月1日までに地方厚生(支)局長へ報告すること。
(9) 許可病床の数が400床以上の病院のうち、前年度1年間の紹介割合の実績が 40%未満又は逆紹介割合の実績が 20‰未満の保険医療機関の取扱いについては、(8)と同様であること。
(10) 「注4」に規定する保険医療機関において、医薬品価格調査の信頼性を確保する観点から、毎年9月末日においても妥結率が低い状況又は妥結率、医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組状況が報告していない状況のまま、初診を行った場合は、特定妥結率初診料を算定する。
(11) 妥結率、医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組状況の取扱いについては、基本診療料施設基準通知の別添1の第2の5を参照のこと。
(12) (11)に規定する報告の際には、保険医療機関と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書の写し等妥結率の根拠となる資料を併せて提出すること。
(13) 現に診療継続中の患者につき、新たに発生した他の傷病で初診を行った場合には、当該新たに発生した傷病について初診料は算定できない。ただし、「注5」のただし書に規定する同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、新たに別の診療科を初診として受診した場合は、現に診療継続中の診療科を除く診療科1つに限り、同ただし書の所定点数を算定できる。また、診療継続中以外の患者であって、同一日に他の傷病で2以上の診療科を初診として受診する場合においても、2つ目の診療科に限り、同ただし書の所定点数を算定できる。この場合において、「注6」から「注 16」までに規定する加算は、算定できない。なお、患者が専門性の高い診療科を適切に受診できるよう保険医療機関が設置した総合外来等については、診療科とみなさず、総合外来等を受診後、新たに別の診療科を受診した場合であっても同ただし書の所定点数は算定できない。
(14) 患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は、初診として取り扱う。なお、この場合において、1月の期間の計算は、例えば、2月10日~3月9日、9月15日~10月14日等と計算する。
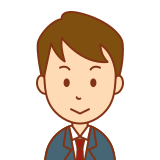
病名登録については、前回までの登録を「中止」で終了させ、初診日で新たに病名登録を行う必要があります。(以下の例題を参照)
(15) (14)にかかわらず、慢性疾患等明らかに同一の疾病又は負傷であると推定される場合の診療は、初診として取り扱わない。
(16) A保険医療機関には、検査又は画像診断の設備がないため、B保険医療機関(特別の関係にあるものを除く。)に対して、診療状況を示す文書を添えてその実施を依頼した場合には、次のように取り扱うものとする。(診療情報提供料(Ⅰ)の(5)から(7)までを参照。)
ア B保険医療機関が単に検査又は画像診断の設備の提供にとどまる場合B保険医療機関においては、診療情報提供料、初診料、検査料、画像診断料等は算定できない。なお、この場合、検査料、画像診断料等を算定するA保険医療機関との間で合議の上、費用の精算を行うものとする。
イ B保険医療機関が、検査又は画像診断の判読も含めて依頼を受けた場合B保険医療機関においては、初診料、検査料、画像診断料等を算定できる。
(17) 乳幼児加算初診料を算定しない場合には、特に規定する場合を除き、「注6」の乳幼児加算は、算定できない。
(18) 時間外加算
ア 各都道府県における医療機関の診療時間の実態、患者の受診上の便宜等を考慮して一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は、午前8時前と正午以降)及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休診日とする保険医療機関における当該休診日とする。ただし、午前中及び午後6時以降を診療時間とする保険医療機関等、当該標準によることが困難な保険医療機関については、その表示する診療時間以外の時間をもって時間外として取り扱うものとする。
イ アにより時間外とされる場合においても、当該保険医療機関が常態として診療応需の態勢をとり、診療時間内と同様の取扱いで診療を行っているときは、時間外の取扱いとはしない。
ウ 保険医療機関は診療時間を分かりやすい場所に表示する。
エ 時間外加算は、保険医療機関の都合(やむを得ない事情の場合を除く。)により時間外に診療が開始された場合は算定できない。
オ 時間外加算を算定する場合には、休日加算、深夜加算、時間外加算の特例又は夜間・早朝等加算については、算定しない。
(19) 休日加算
ア 休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日は、休日として取り扱う。
イ 休日加算は次の患者について算定できるものとする。
(イ) 客観的に休日における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関を受診した患者
① 地域医療支援病院
② 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院又は救急診療所
③ 「救急医療対策の整備事業について」(昭和52年医発第692号)に規定された保険医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険医療機関
(ロ) 当該休日を休診日とする保険医療機関に、又は当該休日を診療日としている保険医療機関の診療時間以外の時間に、急病等やむを得ない理由により受診した患者(上記(イ)以外の理由により常態として又は臨時に当該休日を診療日としている保険医療機関の診療時間内に受診した患者を除く。)
ウ 休日加算を算定する場合には、時間外加算、深夜加算、時間外加算の特例又は夜間・早朝等加算については、算定しない。
(20) 深夜加算
ア 深夜加算は、初診が深夜に開始された場合に算定する。ただし、保険医療機関の都合(やむを得ない事情の場合を除く。)により深夜に診療が開始された場合は算定できない。なお、深夜とは、いずれの季節においても午後10時から午前6時までの間をいう。
イ いわゆる夜間開業の保険医療機関において、当該保険医療機関の診療時間又は診療態勢が午後 10時から午前6時までの間と重複している場合には、当該重複している時間帯における診療については、深夜加算は算定できない。
ウ 深夜加算は、次の患者について算定できるものとする。
(イ) 客観的に深夜における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関を受診した患者
① 地域医療支援病院
② 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所
③ 「救急医療対策の整備事業について」に規定された保険医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険医療機関
(ロ) 自己の表示する診療時間が深夜を含んでいない保険医療機関に、又は自己の表示する診療時間が深夜にまで及んでいる保険医療機関の当該表示する診療時間と重複していない深夜に、急病等やむを得ない理由により受診した患者(上記(イ)以外の理由により常態として又は臨時に当該深夜時間帯を診療時間としている保険医療機関に受診した患者を除く。)
エ 深夜加算を算定する場合には、時間外加算、休日加算、時間外加算の特例又は夜間・早朝等加算については、算定しない。
(21) 時間外加算の特例
ア 当該特例の適用を受ける保険医療機関(以下「時間外特例医療機関」という。)とは、客観的に専ら夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関であって、医療法第 30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている救急医療機関をいう。
① 地域医療支援病院
② 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所
③ 「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院
イ 別に厚生労働大臣が定める時間とは、当該地域において一般の保険医療機関が概ね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜及び休日を除く。)とし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は、午前8時前と正午以降)から、午後10時から午前6時までの間を除いた時間とする。
ウ 時間外特例医療機関において、休日加算又は深夜加算に該当する場合においては、時間外加算の特例を算定せず、それぞれ休日加算、深夜加算を算定する。また、時間外加算の特例を算定する場合には、時間外加算又は夜間・早朝等加算は算定しない。
(22) 小児科(小児外科を含む。以下この部において同じ。)を標榜する保険医療機関における夜間、休日又は深夜の診療に係る特例
ア 夜間、休日及び深夜における小児診療体制の一層の確保を目的として、小児科を標榜する保険医療機関(小児科以外の診療科を併せて有する保険医療機関を含む。)について、6歳未満の乳幼児に対し、夜間、休日又は深夜を診療時間とする保険医療機関において夜間、休日又は深夜に診療が行われた場合にも、それぞれ時間外加算、休日加算又は深夜加算を算定できることとするものである。なお、診療を行う保険医が、小児科以外を担当する保険医であっても算定できるものであること。
イ 夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間とは、当該地域において一般の保険医療機関が概ね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜及び休日を除く。)とし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は、午前8時前と正午以降)から、午後 10時から午前6時までの間を除いた時間とする。
ウ 休日加算の対象となる休日、深夜加算の対象となる深夜の基準は、「注7」に係る休日、深夜の基準の例によるものとする。
エ 時間外加算、休日加算、深夜加算及び夜間・早朝等加算の併算定に係る取扱いは、「注7」の場合と同様である。
(23) 夜間・早朝等加算
ア 夜間・早朝等加算は、病院勤務医の負担の軽減を図るため、軽症の救急患者を地域の身近な診療所において受け止めることが進むよう、診療所の夜間・早朝等の時間帯における診療を評価するものである。
イ 表示する診療時間とは、保険医療機関が診療時間として地域に周知している時間であって、来院した患者を常に診療できる体制にある時間又は計画的に訪問診療を行う時間をいう。この場合において、患者が来院したとしても、診療を受けることのできない時間(定期的に学校医、産業医の業務として保険医療機関を不在とする時間や、地域活動や地域行事に出席するとして保険医療機関を不在とする時間を含む。)は表示する診療時間に含まない。また、診療時間として表示している時間であっても、訪問診療に要する時間以外に、常態として当該保険医療機関に医師が不在となる場合は、表示する診療時間に含めない。
ウ 夜間・早朝等とは、午後6時(土曜日にあっては正午)から午前8時までの間(深夜(午後 10時から午前6時までの間)及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間とする。
エ 往診料を算定した場合にも、初診料に加えて夜間・早朝等加算を算定できる。
オ 夜間・早朝等加算は、当該加算の算定対象となる時間に受付を行った患者について算定するものであり、多数の患者の来院による混雑や、保険医療機関の都合(やむを得ない事情の場合を除く。)により当該加算の算定対象となる時間に診療が開始された場合は算定できない。
カ 診療所の夜間・早朝等の時間帯の診療を評価した夜間・早朝等加算は、主として、保険医療機関が診療応需の態勢を解いた後において、急患等やむを得ない事由により診療を求められた場合には再び診療を行う態勢を準備しなければならないことを考慮して設けられている時間外加算、深夜加算、休日加算とは明確に区分されるものである。
キ「D282-3」コンタクトレンズ検査料、「I010」精神科ナイト・ケア、「J038」人工腎臓の「注1」に規定する加算又は「J038-2」持続緩徐式血液濾過の「注1」に規定する加算を算定する場合においては、夜間・早朝等加算は算定しない。
(24) 機能強化加算
ア「注 10」に規定する機能強化加算は、外来医療における適切な役割分担を図り、専門医療機関への受診の要否の判断等を含むより的確で質の高い診療機能を評価する観点から、かかりつけ医機能を有する医療機関における初診を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た診療所又は許可病床数が200床未満の病院において初診料(「注5」のただし書に規定する2つ目の診療科に係る初診料を除く。)を算定する場合に、加算することができる。
イ 機能強化加算を算定する保険医療機関においては、かかりつけ医機能を有する医療機関として、必要に応じ、患者に対して以下の対応を行うとともに、当該対応を行うことができる旨を院内及びホームページ等に掲示し、必要に応じて患者に対して説明すること。
(イ) 患者が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行うとともに、診療録に記載すること。なお、必要に応じ、担当医の指示を受けた看護職員等が情報の把握を行うことも可能であること。
(ロ) 専門医師又は専門医療機関への紹介を行うこと。
(ハ) 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること。
(ニ) 保健・福祉サービスに係る相談に応じること。
(ホ) 診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行うこと。
(25) 外来感染対策向上加算「注 11」に規定する外来感染対策向上加算は、診療所における、平時からの感染防止対策の実施や、地域の医療機関等が連携して実施する感染症対策への参画、空間的・時間的分離を含む適切な感染対策の下で発熱患者等の外来診療等を実施する体制の確保を更に推進する観点から、外来診療時の感染防止対策に係る体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た診療所において初診料を算定する場合に、患者1人につき月1回に限り加算することができる。
(26) 発熱患者等対応加算「注 11」ただし書に規定する発熱患者等対応加算は、(25)の外来感染対策向上加算を算定している場合であって、発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状を有する患者に空間的・時間的分離を含む適切な感染対策の下で診療を行った場合に算定する。
(27) 連携強化加算「注 12」に規定する連携強化加算は、(25)の外来感染対策向上加算を算定する場合であって、外来感染対策向上加算を算定する保険医療機関が、感染対策向上加算1を算定する保険医療機関に対し、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っている場合に算定する。
(28) サーベイランス強化加算「注 13」に規定するサーベイランス強化加算は、(25)の外来感染対策向上加算を算定する場合であって、外来感染対策向上加算を算定する保険医療機関が、院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加している場合に算定する。
(29) 抗菌薬適正使用体制加算「注14」に規定する抗菌薬適正使用体制加算は、(25)の外来感染対策向上加算を算定する場合であって、外来感染対策向上加算を算定する保険医療機関が抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加し、使用する抗菌薬のうち Access抗菌薬に分類されるものの使用比率が 60%以上又は当該サーベイランスに参加する診療所全体の上位 30%以内である場合に算定する。
(30) 医療情報取得加算
ア 「注15」に規定する医療情報取得加算は、オンライン資格確認を導入している保険医療機関において、初診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で初診を行った場合に、医療情報取得加算1として、月1回に限り3点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項(大正11年法律第70号)に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情報取得加算2として、月1回に限り1点を所定点数に加算する。
イ 医療情報取得加算を算定する保険医療機関においては、以下の事項について院内に掲示するとともに、原則として、ウェブサイトに掲載し、必要に応じて患者に対して説明する。
(イ) オンライン資格確認を行う体制を有していること。
(ロ) 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。
ウ 初診時の標準的な問診票の項目は別紙様式54に定めるとおりであり、医療情報取得加算を算定する保険医療機関は、患者に対する初診時問診票の項目について、別紙様式54を参考とする。
(31) 医療DX推進体制整備加算
「注16」に規定する医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報等を実際の診療に活用できる体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合に、月1回に限り8点を所定点数に加算する。
情報通信機器を用いた診療に係る施設基準
(1) 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されているものとして、以下のア~エを満たすこと。
ア 保険医療機関外で診療を実施することがあらかじめ想定される場合においては、実施場所が厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(オンライン指針)に該当しており、事後的に確認が可能であること。
イ 対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められていることを踏まえて、対面診療を提供できる体制を有すること。
ウ 患者の状況によって当該保険医療機関において対面診療を提供することが困難な場合に、他の保険医療機関と連携して対応できること。
エ 情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行わないことを当該保険医療機関のホームページ等に掲示していること。
(2) オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
夜間・早朝等加算に関する施設基準等
(1) 1週間当たりの表示診療時間の合計が 30 時間以上の診療所である保険医療機関であること。なお、一定の決まった日又は決まった時間に行われる訪問診療の時間については、その実施する時間を表示している場合に限り、1週間当たりの表示診療時間に含めて差し支えない。
(2) (1)の規定にかかわらず、概ね月1回以上、当該診療所の保険医が、客観的に深夜における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関に赴き夜間・休日の診療に協力している場合は、1週間当たりの表示診療時間の合計が27時間以上でよいこと。また、当該診療所が次のイ及びウの保険医療機関である場合も同様に取り扱うものであること。
ア 地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)
イ 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院又は救急診療所
ウ 「救急医療対策の整備事業について(昭和52年医発第692号)」に規定された保険医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険医療機関
(3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、表示診療時間とされる場合であって、当該診療所が常態として医師が不在となる時間(訪問診療に要する時間を除く。)は、1週間当たりの表示診療時間の合計に含めない。
(4) 診療時間については、当該保険医療機関の建造物の外部かつ敷地内に表示し、診療可能な時間を地域に周知していること。なお、当該保険医療機関が建造物の一部を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の外部に表示していること。
機能強化加算に関する施設基準
次のいずれにも該当すること。
(1) 診療所又は許可病床数が200床未満の病院であること。
(2) 次のいずれかを満たしていること。
ア 再診料の注12に規定する地域包括診療加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
イ 以下のいずれも満たすものであること。
(イ) 再診料の注12に規定する地域包括診療加算2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(ロ) 直近1年間において、次のいずれかを満たしていること。
① 再診料の注12に規定する地域包括診療加算2を算定した患者が3人以上
② 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)又は往診料を算定した患者の数の合計が3人以上
ウ 地域包括診療料1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
エ 以下のいずれも満たすものであること。
(イ) 地域包括診療料2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(ロ) 直近1年間において、次のいずれかを満たしていること。
① に掲げる地域包括診療料2を算定した患者が3人以上
② 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)又は往診料を算定した患者の数の合計が3人以上
オ 小児かかりつけ診療料1又は2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
カ 在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料に係る届出を行っている保険医療機関であって、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添1の第9在宅療養支援診療所の1 (1)若しくは(2)に該当する診療所又は第14の2在宅療養支援病院の1(1)若しくは(2) に該当する病院であること。
キ 施設入居時等医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料に係る届出を行っている保険医療機関であって、特掲診療料施設基準通知の別添1の第9在宅療養支援診療所の1(3)に該当する診療所並びに第14の2在宅療養支援病院の1(3)に該当する病院であり、以下のいずれかを満たしていること。
(ロ) 第9在宅療養支援診療所の1(3)に該当する診療所であって、以下のいずれかを満たしていること。なお、緊急の往診の実績及び在宅における看取りの実績等の取扱いについては、第9在宅療養支援診療所と同様である。
① 第9在宅療養支援診療所の1(1)コに掲げる過去1年間の緊急の往診の実績が3件以上
② 第9在宅療養支援診療所の1(1)サに掲げる過去1年間の在宅における看取りの実績が1件以上又は過去1年間の 15 歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績が1件以上
(ハ) 第14の2在宅療養支援病院の1(3)に該当する病院であって、以下のいずれかを満たしていること。なお、緊急の往診の実績及び在宅における看取りの実績等の取扱いについては、第14の2在宅療養支援病院と同様である。
① 第14の2在宅療養支援病院の1(1)シ①に掲げる過去1年間の緊急の往診の実績又は1(1)シ②に掲げる在宅療養支援診療所等からの要請により患者の緊急受入を行った実績の合計が直近1年間で3件以上
② 第14の2在宅療養支援病院の1(1)スに掲げる過去1年間の在宅における看取りの実績が1件以上又は過去1年間の 15 歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績が1件以上
(3) 地域における保健・福祉・行政サービス等に係る対応として、以下のいずれかを行っている常勤の医師を配置していること。
ア 介護保険制度の利用等に関する相談への対応及び要介護認定に係る主治医意見書の作成を行っていること。
イ 警察医として協力していること。
ウ 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条に規定する乳幼児の健康診査(市町村を実施主体とする1歳6か月、3歳児等の乳幼児の健康診査)を実施していること。
エ 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(定期予防接種)を実施していること。
オ 幼稚園の園医、保育所の嘱託医又は小学校、中学校若しくは高等学校の学校医に就任していること。カ 「地域包括支援センターの設置運営について」に規定する地域ケア会議に出席していること。
キ 通いの場や講演会等の市町村が行う一般介護予防事業に協力していること。
(4) 地域におけるかかりつけ医機能として、必要に応じ、以下のアからオの対応を行っていること。また、当該対応を行っていることについて当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。
ア 患者が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行うこと。
イ 専門医師又は専門医療機関への紹介を行うこと。
ウ 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること。
エ 保健・福祉サービスに関する相談に応じること。
オ 診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行うこと。
また、医療機能情報提供制度を利用してかかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関を検索できることを、当該医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(5) (4)に基づき掲示している内容を記載した文書を当該保険医療機関内の見やすい場所に置き、患者が持ち帰ることができるようにすること。また、患者の求めがあった場合には、当該文書を交付すること。
外来感染対策向上加算に関する施設基準
次のいずれにも該当すること。
(1) 診療所であること。
(2) 感染防止に係る部門「以下「感染防止対策部門」という。」を設置していること。ただし、別添3の第20の1の(1)イに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策部門としても差し支えない。
(3) 感染防止対策部門内に、専任の医師、看護師又は薬剤師その他の医療有資格者が院内感染管理者として配置されており、感染防止に係る日常業務を行うこと。なお、当該職員は別添3の第20の1の(1)アに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理者とは兼任できないが、医科点数表第1章第2部通則7に規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行うことができる。
(4) 感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者の具体的な業務内容が整備されていること。
(5) (3)の院内感染管理者により、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、各部署に配布していること。
(6) (3)の院内感染管理者により、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。なお、当該研修は別添2の第1の3の(5)に規定する安全管理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。
(7) (3)の院内感染管理者は、少なくとも年2回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること。なお、感染対策向上加算1に係る届出を行った複数の医療機関と連携する場合は、当該複数の医療機関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年1回参加し、合わせて年2回以上参加していること。また、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が主催する、新興感染症の発生等を想定した訓練については、少なくとも年1回以上参加していること。
(8) (7)に規定するカンファレンスは、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。
(9) 院内の抗菌薬の適正使用について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会から助言を受けること。また、細菌学的検査を外部委託している場合は、薬剤感受性検査に関する詳細な契約内容を確認し、検査体制を整えておくなど、「中小病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」に沿った対応を行っていること。
(10) (3)の院内感染管理者により、1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。
(11) 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示していること。
(12) 当該保険医療機関の外来において、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者の受入れを行う旨を公表し、受入れを行うために必要な感染防止対策として、空間的・時間的分離により発熱患者等の動線を分ける等の対応を行う体制を有していること。
(13) 感染症法第38条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第二種協定指定医療機関(同法第36条の2第1項の規定による通知(同項第2号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく措置を講ずる医療機関に限る。)であること。
(14) 新興感染症の発生時等に、発熱患者等の診療を実施することを念頭に、発熱患者等の動線を分けることができる体制を有すること。
(15) 厚生労働省健康局結核感染症課「抗微生物薬適正使用の手引き」を参考に、抗菌薬の適正な使用の推進に資する取組を行っていること。
(16) 新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応を想定した地域連携に係る体制について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関等とあらかじめ協議されていること。
(17) 感染症から回復した患者の罹患後症状が持続している場合に、当該患者の診療について必要に応じて精密検査が可能な体制又は専門医への紹介が可能な連携体制を有していることが望ましい。
(18) 感染対策向上加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
連携強化加算に関する施設基準
次のいずれにも該当すること。
(1) 外来感染対策向上加算に係る届出を行っていること。
(2) 当該保険医療機関が連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関に対し、過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っていること。
サーベイランス強化加算に関する施設基準
(1) 外来感染対策向上加算に係る届出を行っていること。
(2) 院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること。
抗菌薬適正使用体制加算に関する施設基準
(1) 外来感染対策向上加算に係る届出を行っていること。
(2) 抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加していること。
(3) 直近6か月における使用する抗菌薬のうち、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又は(2)のサーベイランスに参加する診療所全体の上位30%以内であること。
医療情報取得加算に関する施設基準
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(3) 次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。
イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
医療DX推進体制整備加算に関する施設基準
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) オンライン資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(3) オンライン資格確認等システムの活用により、患者の薬剤情報、特定健診情報等(以下この項において「診療情報等」という。)を診療を行う診察室、手術室又は処置室等(以下「診察室等」という。)において、医師等が閲覧又は活用できる体制を有していること。
(4) 「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有していること。
(5) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。
(6) マイナ保険証の利用率が一定割合以上であること。
(7) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること
イ マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。
ウ 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること。
(8) (7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。





